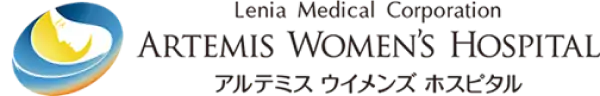小児予防接種
予防接種は乳幼児期だけでなく、3歳以降も重要なワクチンが複数あります。とくに就学前後の麻しん風しん混合ワクチン(MR)2期、日本脳炎、思春期の子宮頸がんワクチン(HPV)、二種混合(DT)などは、忘れずに接種しましょう。
日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュールを参考に、年齢に応じた計画的な接種を心がけましょう。
※定期接種は多くの場合、市区町村から予診票やお知らせが届きますが、転居などで届かないこともあります。対象年齢を過ぎると公費での接種ができなくなるため、通知がなくてもスケジュールを確認し、計画的に進めましょう。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
※小児科での診療は中学三年生の3月末までとなり、それ以降の方は成人として、女性内科または婦人科での対応となります。
| 区分 | ワクチン名 | 対象・回数など | 自費料金(税込) | 公費 |
|---|---|---|---|---|
| 小児 | 肺炎球菌(20価) | 対象・回数など4回接種 | 自費料金(税込み)12,500円/回 | 公費〇 |
| B型肝炎 | 対象・回数など3回接種 | 自費料金(税込み)5,500円/回 | 公費〇 | |
| ロタウイルス(ロタリックス) | 対象・回数など2回接種 | 自費料金(税込み)14,960円/回 | 公費〇 | |
| 5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib) |
対象・回数など4回接種 | 自費料金(税込み)20,000円/回 | 公費〇 | |
| 麻しん風しん(MR) | 対象・回数など2回接種 | 自費料金(税込み)7,920円/回 | 公費〇 | |
| 水痘(みずぼうそう) | 対象・回数など2回接種 | 自費料金(税込み)8,690円/回 | 公費〇 | |
| おたふくかぜ | 対象・回数など2回接種 | 自費料金(税込み)5,170円/回 | 公費― | |
| 日本脳炎 | 対象・回数など4回接種 | 自費料金(税込み)7,700円/回 | 公費〇 | |
| 2種混合(DT) | 対象・回数など1回接種 | 自費料金(税込み)5,500円/回 | 公費〇 | |
| 子宮頸がんワクチン(HPV)シルガード9 | 対象・回数など2回または3回接種 | 自費料金(税込み)初回:30,800円/回
2回目~:28,600円/回 |
公費〇 | |
| A型肝炎 | 対象・回数など3回接種 | 自費料金(税込み)7,700円/回
4/1~:17,000円/回 |
公費― | |
| インフルエンザ(注射) | 対象・回数など2回接種(6か月~12歳)
1回接種(13歳~) |
自費料金(税込み)3,400円/回 | 公費― | |
| インフルエンザ(経鼻)フルミスト | 対象・回数など1回接種(2歳~18歳) | 自費料金(税込み)7,700円/回 | 公費― |
東久留米市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市の予診票をお持ちの方は無料になる場合があります。
詳細は各市の予防接種係にお問い合わせください。
受付時間
月〜金:11:30、14:30、16:30
土:11:30、12:00、12:30(午後は休診)
予約方法
1回の接種分のみ予約可能です。
予約はWEB予約でお願いします。(経鼻インフルエンザワクチン〔フルミスト〕のみ電話予約となります。042-472-6111)
兄弟姉妹で同日接種を希望する場合は、人数分の予約をお取りください。
小児の予防接種漏れを防ぐために接種履歴の登録をお願いします。他院の接種履歴・BCGの接種履歴も登録してください。
保護者の同伴について
東久留米市の規定により、小児科での定期接種には、保護者(※1)の同伴が必要です。保護者が同伴できない場合は、必ず保護者の委任状(※2)をご持参ください。
※1 東久留米市による「保護者」の定義は、以下のいずれかに該当する方です:①父母 ②未成年後見人 ③養子縁組をしている祖父母
※2 委任状の書式は問いません。当院規定の書式(PDF)はこちらからダウンロードいただけます。
接種当日の持ち物
- 母子手帳(必須)
- 予診票(市から送付されたもの、または当院指定用紙)
- マイナ保険証または資格確認書、医療証(本人確認のため)
- 委任状(必要な方のみ)
成人予防接種
予防接種は、年齢やライフステージに応じて感染症を予防し、重症化を防ぐための大切な手段です。
妊婦の方には、RSウイルス感染予防のためのワクチン(アブリスボ)やインフルエンザワクチンが推奨されています。
妊娠を希望される方は、風しん抗体価を確認し、必要に応じて、風しんまたはMRワクチンの接種を検討しましょう。
成人の方では、麻しん風しん混合(MR)、B型肝炎、子宮頸がん、肺炎球菌、インフルエンザなどのワクチンが、健康維持のために推奨されています。年齢や体調に合わせたワクチン接種の機会を逃さないようにしましょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
| 区分 | ワクチン名 | 対象・回数など | 自費料金(税込) | 公費 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊婦 | RSウイルス(アブリスボ) | 対象・回数など妊娠24〜36週で1回接種 | 自費料金(税込)32,000円/回 | 公費― | 特記事項RSウイルス感染症に対する有効性は、接種後14日以内出生児で未確立、生後6カ月まで検証済。他のワクチンと同時接種可。 |
| インフルエンザ | 対象・回数など妊娠中も接種可 | 自費料金(税込)4,200円/回 | 公費― | 特記事項― | |
| 妊娠希望 | 風しん(単独) | 対象・回数など抗体価により接種 | 自費料金(税込)4,400円/回 | 公費△ | 特記事項一部助成あり |
| 成人 | MR(麻しん風しん混合) | 対象・回数など必要に応じて | 自費料金(税込)7,920円/回 | 公費〇 | 特記事項― |
| 麻しん(単独) | 対象・回数など必要に応じて | 自費料金(税込)7,700円/回 | 公費― | 特記事項― | |
| 風しん(単独) | 対象・回数など必要に応じて | 自費料金(税込)4,400円/回 | 公費― | 特記事項― | |
| A型肝炎 | 対象・回数など3回接種 | 自費料金(税込み)7,700円/回
4/1~:17,000円/回 |
公費― | 特記事項― | B型肝炎 | 対象・回数など3回接種 | 自費料金(税込)5,500円/回 | 公費― | 特記事項― |
| 子宮頸がんワクチン(HPV)シルガード9 | 対象・回数など2回または3回接種 | 自費料金(税込)初回:30,800円/回
2回目~:28,600円/回 |
公費― | 特記事項― | |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 対象・回数など1回接種 | 自費料金(税込)7,700円/回 | 公費△ | 特記事項65歳以上は助成あり | |
| インフルエンザ | 対象・回数など1回接種 | 自費料金(税込)4,200円/回 | 公費△ | 特記事項65歳以上は助成あり | |
| 帯状疱疹(水痘ワクチン) | 対象・回数など1回接種 | 自費料金(税込)8,690円/回 | 公費△ | 特記事項65歳以上は助成あり | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 対象・回数など2回接種 | 自費料金(税込)21,450円/回 | 公費△ | 特記事項65歳以上は助成あり |
東久留米市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市の予診票をお持ちの方は無料になる場合があります。
詳細は各市の予防接種係にお問い合わせください。
受付時間
月〜金:9:00〜12:00/14:00〜17:00
土曜日:9:00〜12:30(午後休診)
予約方法
予約は電話で受け付けています。
042-472-6111
接種当日の持ち物
- マイナ保険証または資格確認書
- 診察券
- 予診票